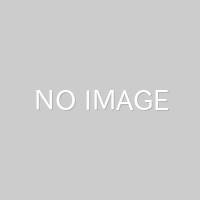安藤忠雄展と万博と出家功徳

先ほど大阪から戻りました。無事に全日程の用事を済ませ久しぶりの関西を楽しみました。大阪駅から徒歩10分のところにVS.(グラングリーン大阪内)という施設がありそこで今回は「安藤忠雄展 青春」が開催されておりました。ここに来れただけでも幸せを感じていたのにまさか当の本人が来館しているとは思わず感動もひとしおでした。講演会にも参加できました。終わって図鑑に直筆のサインもしていただきました。この1ヶ月は安藤忠雄さんの建築作品を何度も動画で見て研究をしておりました。時には一日中、安藤建築に魅せられてひたすら見入っていたことさえありました。あまりにものめり込み葬儀の時の法話にも安藤忠雄の人なりを話させていただいておりました。その功ありなのか図らずも本人にお目にかかることができ夢が叶った気分になりました。いずれは安藤忠雄建築研究所に依頼して美術館的書院をつくるという夢構想を描いている矢先の出来事でした。私も思ったらひたすらにそのことに没頭する性分です。そのことを思い続けて無我夢中になる性格です。また一つ夢がカタチになりました。現実に一歩でも近づければよいと思います。帰りの新幹線の車中も安藤作品の図鑑に目をやり構想を膨らませておりました。今日は朝から大阪・関西万博の会場である夢洲へと向かいました。炎天下の人だかりの中をなんとか会場入りできました。厳重な警備、荷物検査もありました。場内は想像を超える広さであり圧巻でありました。とても1日、2日で見て回れる規模ではありません。早々に諦めて全体を俯瞰すべく木組みのリングサイドを一周して帰路に着くことに変更しました。二日間でしたが充実した時を過ごせたと思います。心機一転の気分転換にもなりました。英気を養うこともできました。感謝感謝です。
あと三ヶ月で還暦のため仕上げをするべくまとめに入って来ております。なんとか見通しは立って来ております。お楽しみにしてください。そして第二の人生は本物の僧侶を育成するための準備もしていきます。もはや終活や供養産業をマネタイズ(収益化)できるほど時代は甘くはありません。習慣化し、慣習化した先祖教も皮肉にも先祖返りをして劣化しました。需要はなくなりつつあります。今は求められていない需要を追いかけているのが僧侶です。葬儀もお墓も仏壇もいらないという時代にこれで飯を食ってはいけません。当然に拝み屋としての僧侶はいらなくなります。需給バランスが崩れたので僧侶減少はよいことかもしれません。あとは僧侶以外で何ができるかが問われます。とても厳しい時代です。副業も選択肢ですが内容にもよります。二足の草鞋を履いても利害が一致するかが重要です。あとは本物になって信者をつくれるかです。僧侶に求められるものは二つです。智慧と慈悲です。これを備えるしかありません。これが欠けている僧侶があまりにも多過ぎます。何のために僧侶は存在しているのでしょうか。この存在価値が見出せなかったらやっている意味などまるでありません。なぜあなたは出家をしたのですか。それによって何をしたいのですか。あなたがお坊さんでい続けることによって世の中はどう変わるのですか。これに応えられる人だけがすべき事柄です。檀家には誰もならないはずです。だから私は四十代、五十代の出家は基本的には認めないという持論はあります。また社会で挫折をしてお坊さんになって見返したいという出家の動機者は論外です。
これまで私も一般家庭からの出家者を見て来ましたがほぼ落第点です。まだ羅睺羅(お寺の息子)の方がこれでもましという結論に至りました。尼僧様も意外と曲者だらけでした。この世界は本当に腐っていると思います。だからこそ真の出家者は必要です。これからはこれまでの教訓を踏まえて志のある優秀な人に限って弟子にすることにしました。そういう人が現れるまでは待ちます。こちらからは決して斡旋はしません。懲りました。瓦解していく社会ですからなおさらです。不用意に粗製濫造をさせてはいけないと思います。厳選に厳選をしていく時代のように思います。もはや世間から求められてもいないし期待もされてはいません。むしろ名誉挽回の時です。淘汰の中で這い上がっていくしかないと思います。金目当てばかりの僧侶がこれ以上増えても意味がありません。10人いや100人の堕落僧よりも1人の傑僧です。お寺や僧侶はもういらないと思います。宗務庁や大本山にも求心力はなくなります。一人一人がどうするかの方がよっぽど大事です。そこに目覚める時です。権威主義は不要です。肝心なのは本質です。見かけはもう結構です。ただ威張っているだけの僧侶は疎外されます。阻害の要因になっているだけです。
実際に昨日、間近で安藤忠雄さんにお会いしてみて闘争心でやって来たという割にはとても温厚でやさしく見えました。一時代を築き身を粉にして働き不朽の名作を数々、世に送り出して来た巨匠です。なんとも言えないオーラが漂っておりました。僧侶にもこのような光明が射すようでなかったらいけません。仏像には必ず光背があります。後光が射しております。それにはその道に精進精進をするしかないと思います。脇目も振らずにまっしぐらに突き進む人生を私も歩みたいものです。
令和7年5月14日
見性院住職